設計の理想と現実の間で揺れる時期、それが基本設計前回は「構想設計」で、“あたりをつける”思考法についてお話ししました。
今回は、その構想を実際の「形」に落とし込む段階
――基本設計です。
基本設計は、理想的なアイデアと現実の制約の間で揺れ動く重要なプロセスです。
この段階での決断が、製品の成功を大きく左右します。
基本設計とは――構想を「形」に変えるステップ
基本設計は、構想設計で描いたスケッチをもとに、材料の種類、板厚、寸法、構造などを具体的に決めていく段階です。
まだ図面を完成させる前段階ですが、ここで決まる内容は非常に重要です。
基本設計の判断が、製品の性能・コスト・安全性を8割決めるからです。
言い換えれば、「紙の上で最もお金を動かしているのが基本設計者」。
設計者が“経営的視点”を持つべき理由もここにあります。
三つ巴の関係:機能・強度・コストのトレードオフ
設計者がいつも頭を抱えるのがこの三角関係です。
機能:高性能になるが、複雑化・高コスト化。シンプルだが、性能不足の恐れ。
強度:壊れにくく安全だが、重く高価に。軽く安いが、寿命が短くなる。
コスト:安くできるが、性能や寿命を犠牲に。高品質になるが、利益が減る。
この三つはすべてを同時に高めることはできません。
だからこそ設計者は、「どこにお金をかけ、どこを割り切るか」を考える必要があります。
そしてこの3つの上位には、安全第一があるのです。
圧力鍋に学ぶ、設計のバランス感覚
たとえば圧力鍋。
簡単な構造であれば、厚い金属で作ればいい。
しかしそれでは重く、高価になり、扱いにくくなります。
一方で薄くすれば軽く安くなりますが、耐久性が落ちる。
このとき設計者は、「必要十分な強度」を探します。
つまり、“壊れないギリギリではなく、壊れにくい最小限”のラインを見極めるのです。
身近な自転車でも同じです。
レース用なら軽さを優先してカーボン素材に、通勤用ならコストと耐久性を考えてアルミやスチールに。
どちらも“正解”ですが、目的によって最適解は変わるのです。
数字で考える:ExcelやCAEで“あたり”をつける
この段階では、設計者の勘だけでなく、数字による裏づけが大切です。
私はよくExcelで「簡易計算シート」を作ります。
たとえば、板厚を2mmから3mmに変えたときの重量増加、材料費、加工時間を計算し、「どこまで厚くしても採算が取れるか」を目で確認します。
また、近年はCAE(Computer Aided Engineering)を活用する設計も一般的です。
これは、コンピュータ上で応力や変形をシミュレーションできるツールです。
実際に試作する前に、どの部分が弱いかを“見える化”できます。
ただし、CAEの結果を過信するのは禁物です。
あくまで「仮説を確かめる道具」であり、判断するのは人間の経験です。
若手設計者が知っておきたい「見積り思考」
基本設計のもう一つの重要ポイントが「見積り思考」です。
つまり、「この設計がいくらで作れるのか」を感覚的につかむ力です。
材料費、加工費、溶接・組立・検査コスト
――すべては設計段階でほぼ決まります。
ベテラン設計者は、図面を描く前に頭の中で“ざっくり見積り”をしています。
私の場合、「この溶接を減らせば1時間分の工賃が浮くな」といった感覚。
こうした“数字の感覚”が身につくと、設計の精度が一気に上がります。
まとめ:設計の最適化は、数字と感性の両立から生まれる
基本設計は、まさに理想と現実のせめぎ合いです。
計算上は理想的でも、現場では加工できないこともあります。
コストを削っても、信頼性を失えば意味がありません。
だから設計者には、「数字で語れる冷静さ」と「人の感覚を想像できる温かさ」
――この両方が求められます。
最後に、私が若手時代に上司から言われた言葉を贈ります。
「設計とは、数字で証明し、心で納得させる仕事だ。」
次回は、「詳細設計 ― 図面に魂を吹き込む」をテーマに、寸法、公差、加工性など、設計の“最終段階”を一緒に掘り下げていきましょう。
さむらいすけ
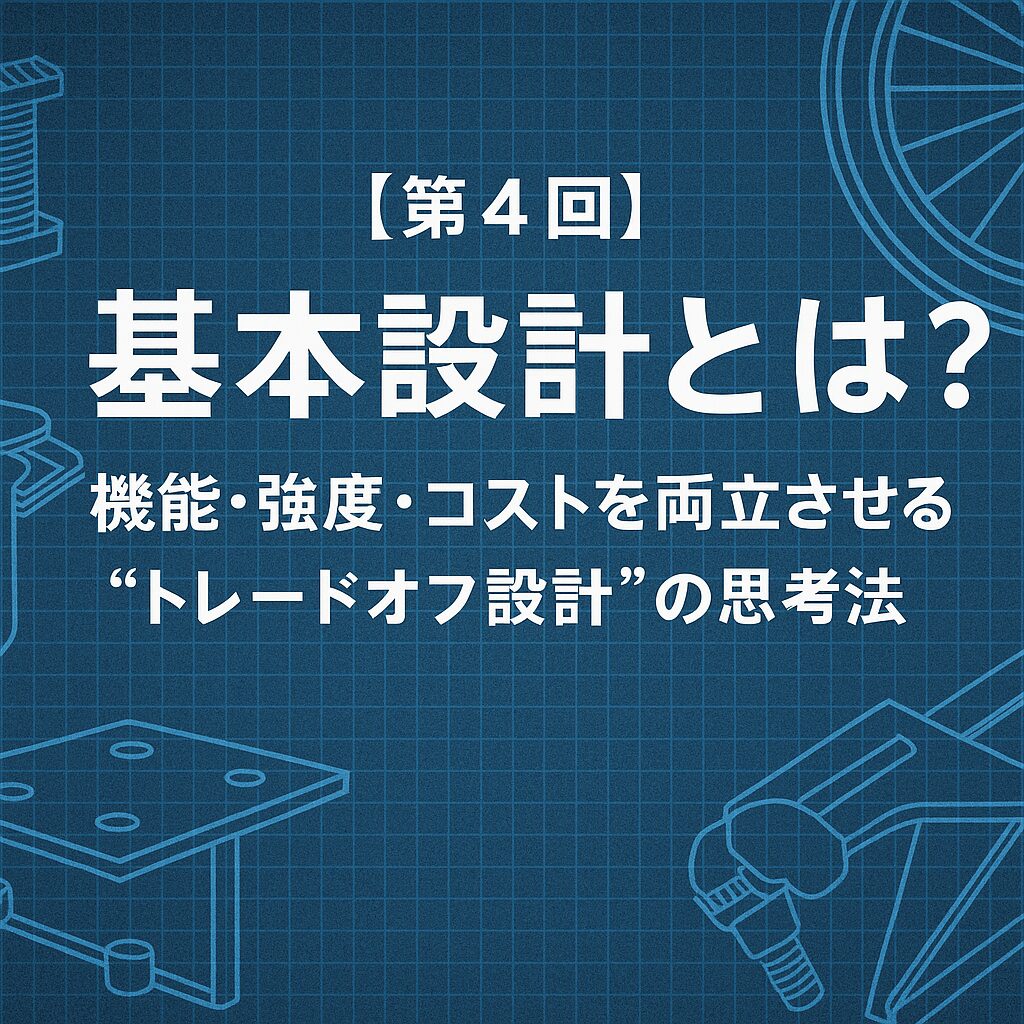

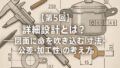
コメント