図面の前に、まず考える「構想設計」とは?
前回は「企画の段階」で、お客様の“本当の要求”を見抜く力についてお話ししました。
今回はいよいよ設計の中心
――構想設計についてです。
図面の前にある「構想設計」という思考時間
若手エンジニアからよく聞く質問があります。
「構想設計って、具体的に何をするんですか?」
いい質問です。
簡単に言うと、構想設計とは「目的を実現するための全体の仕組みを考える段階」です。
まだ図面を描く前の、“設計の設計”とも言えます。
例えば、「自動でフタが開くゴミ箱を作りたい」と言われたら、
センサーで人を検知してモーターで開けるのか
足でペダルを踏んで開けるのか
上にスライドするのか、
横に開くのか
これらの“仕組み”を考えるのが構想設計です。
この段階では、CADよりも紙と鉛筆の方が早い。
むしろ、手を動かす前に頭を動かすことが大切なんです。
構想設計は「思考のスケッチ」
構想設計は、最初から完璧を目指す必要はありません。
むしろ“ラフスケッチ”のように、頭の中のイメージをどんどん描き出す作業です。
私も若手のころ、ノートに無数の落書きをしていました。
線が歪んでも、アイデアが未完成でも構わない。
重要なのは、考えた形を「見える化」すること。
たとえば、圧力鍋のフタのロック機構を考えるなら、「回して締める」「押してロックする」「バネで自動固定」など、3~4案を簡単にスケッチして、それぞれのメリット・デメリットを比較するのです。
構想設計とは、アイデアを“ふるいにかける時間”。
頭の中に浮かんだ案を出し切ってから、現実的なものを選ぶ
――これがベテラン設計者の基本姿勢です。
圧力鍋で考える構想の違い
圧力鍋を設計する場合、「安全」「時短」「使いやすさ」の3つがポイントです。
安全性を高めるために二重ロック構造にすれば安心ですが、コストが上がる。
逆に構造を簡単にすれば安く作れますが、事故のリスクが増える。
つまり構想設計とは、どんな性能を重視するかを決める作業でもあります。
それを「設計方針」と呼びます。
“あたりをつける”という設計者の感覚
構想設計をするとき、私はいつも「あたりをつける」という言葉を意識します。
これは「正解を見つける」のとは違います。
“だいたいこの方向ならいけそうだ”という勘のような判断です。
例えば、流体を扱う装置を設計するなら、まず配管の流れを手描きで描き、圧力損失をざっくり計算します。
完璧な値ではなくても、「このサイズなら成立するな」と“あたり”をつける。
この感覚は、経験からしか身につきませんが、誰でもできます。
重要なのは、数字で裏づける前に仮説を立てることです。
設計は、考えて→試して→修正する。
その繰り返しで強くなります。
若手エンジニアに伝えたい「考える順番」
構想設計では、次の順番で考えると整理しやすいです。
1. 目的を言葉で書く(例:「軽くて安全な自転車を設計する」)
2. 必要な要素を洗い出す(フレーム、タイヤ、チェーン、ブレーキ)
3. それぞれの要素の関係を描く(どこを動かす?どこを支える?)
4. 複数の案を出して比較する(軽さ優先型、コスト優先型、スピード優先型など)
ここで大切なのは、「手段」ではなく「目的」に立ち返ること。
若手のうちは、どうしても“部品の形”に目が行きがちですが、設計の本質は全体のつながり(構造)を考えることにあります。
まとめ:構想設計は、最初の失敗を“紙の上で”する時間
ベテランになって痛感するのは、「紙の上での失敗はタダだが、現場での失敗は高くつく」ということです。
構想設計の段階でどれだけ頭をひねったかが、その後の品質を決めます。
だから私は、若手にいつもこう伝えています。
「図面を描く前に、ノートが真っ黒になるまで考えよう。」
構想設計とは、失敗を先取りして、成功への道筋を描く作業です。
次回は、「基本設計――シンプルで壊れにくい構造を考える」をテーマに、実際に形を決めていく段階を一緒に見ていきましょう。
さむらいすけ
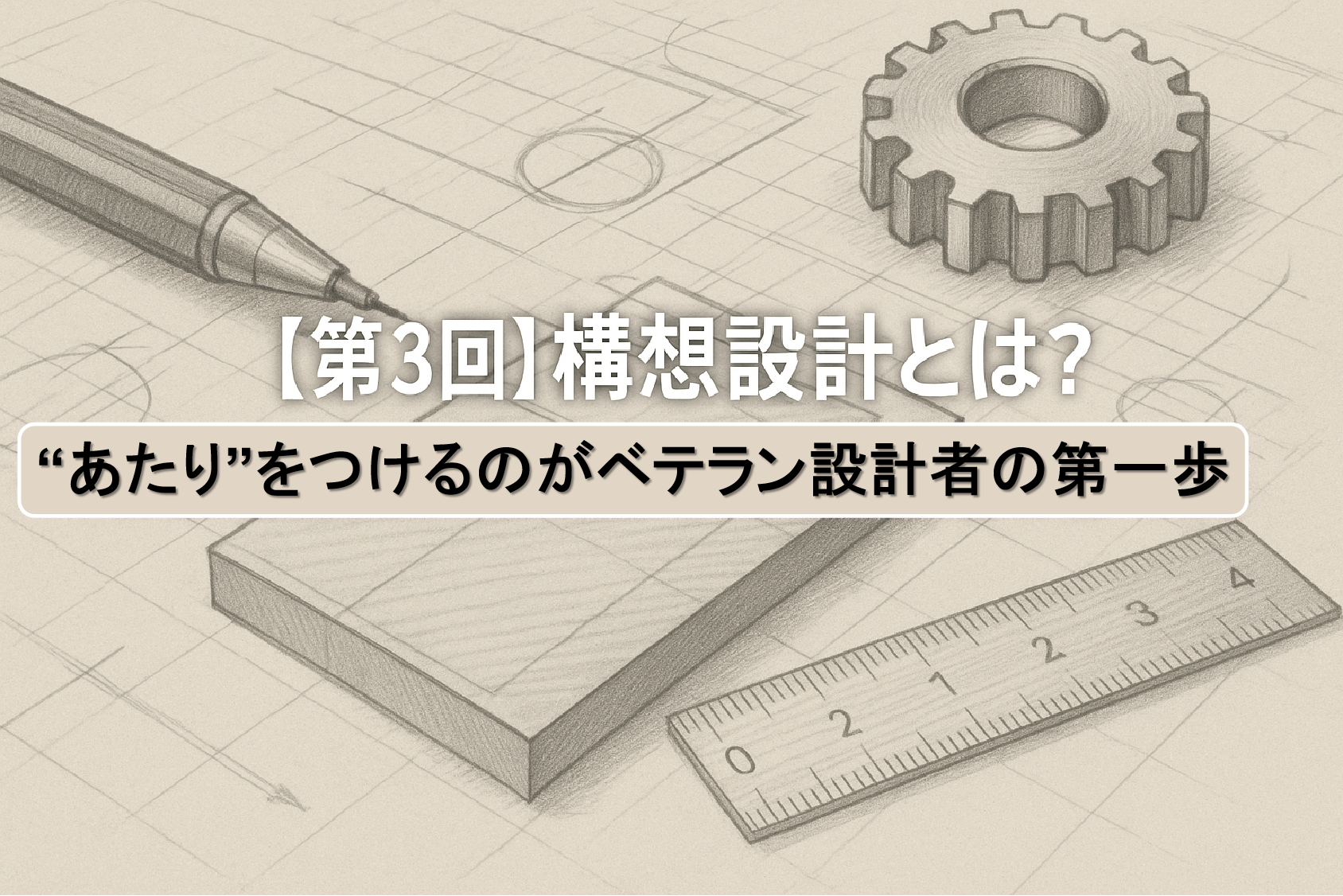
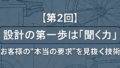

コメント