今回は、私が長年携わってきた機械設計のもう一つの顔
――それは「総合格闘技」のようなチームワークの面白さについてお話ししたいと思います。
「設計者」と聞いて、机に向かって一人で黙々と図面を描いている姿を思い浮かべる人も多いでしょう。
しかし現実はまるで違います。
私たちが手掛けるプラント設備や圧力容器のような巨大な「モノ」は、設計者ひとりの力で完成するものではありません。
解析、調達、製造、品質検査、工務、営業…
数えきれないほどのプロフェッショナルが関わり、知恵と技術を持ち寄りながら、
ようやく形になるのです。
この「チームで挑むモノづくり」こそが、機械設計という仕事の醍醐味であり、最大のやりがいなのです。
チームで働くということ解析担当、調達、製造現場、品質検査
――みんなで一つの製品を完成させる「総合格闘技」
チームで繋ぐリレー
機械設計を支える仲間たち製品の設計は、多くの情報を収集し、複数の設計者や関係部署と密にコミュニケーションを取りながら進める必要があります。
まさに、各部門がバトンを繋ぎ、目標達成のために全員でゴールに向かう「チーム」の定義そのものです。
1. 解析担当:設計の「頭脳」
「この構造は本当に強度を持つのか?」「熱で歪まないか?」
――設計段階で出てくる不安を、数値解析とシミュレーションで解き明かしてくれるのが解析担当です。
彼らの冷静なフィードバックがなければ、設計は机上の空論で終わってしまいます。
私自身、過去に解析担当から「この案では熱で5mmも変形する」と突き返された経験があり、その時こそ「設計は一人では完結しない」と痛感しました。
複雑な要素を考慮する機械設計において、論理的思考で最適解を導き出す彼らは、まさしく設計の「頭脳」です。
2. 調達部:モノづくりの「血液」を流す
優れた設計も、材料がなければただの絵です。
調達部は、必要な品質・納期・コストを満たす材料や部品を国内外から探し出してくれます。
ときには新しい素材や工法を提案してくれることもあり、設計の可能性を大きく広げてくれる存在です。
プラント設計では、調達した設備のレビューも重要な業務の一部となります。
3. 製造現場:設計を「具現化」する腕
鉄やステンレスの塊を実際に加工し、図面を形にするのが製造現場です。
「この溶接は狭すぎて難しい」「この寸法は現場だと加工しづらい」
――こうしたリアルな声は、設計者だけでは気づけない現実の壁です。
私は現場に足を運び、職人と直接話すことで、初めて“生きた設計”ができるようになりました。
設計者は黙々と図面に向き合うだけでなく、現場の人たちとコミュニケーションを取ることが不可欠なのです。
4. 品質検査部:製品の「守護神」
完成した製品が設計通りかを厳しくチェックするのが品質検査部です。会社によっては品質保証部ともいうでしょう。
彼らが見逃さないからこそ、私たちは安心して製品を世に送り出せます。
厳しい指摘を受けることもありますが、それがあるからこそ信頼が積み重なるのです。
品質検査は、プラント完成後の重要な業務の一つでもあります。
5. 工務部:見えない「司令塔」
工務部は、機器の輸送手配や購入品のスケジュール管理を担い、全体の工程を滑らかに進める存在です。
彼らの調整力が欠ければ、現場で部品が届かず作業が止まることもあります。
まさに縁の下の力持ちです。
特に大規模なプラント建設プロジェクトでは、プロジェクト遂行に関わる組織が複雑化するため、工務部のような司令塔の役割は非常に重要になります。
6. 営業部と顧客:ゴールを共有する仲間
営業部は顧客の声を設計者に届け、完成した製品の価値を社会に広げます。
最終的に顧客が喜び、社会に役立つことこそが、私たち全員のゴールです。
機械設計は、エンジニアリングや製造だけでなく、マーケティングや販売部門とも意見を交換し、協力して進めることが求められます。
苦い失敗から学んだこと多くのプロが関わる「総合格闘技」だからこそ、コミュニケーション不足や部門間の連携の難しさが課題となることがあります。
私も、リーダーとしてこの壁に直面し、苦い経験をしました。
私が忘れられない失敗は、海外の大型プラントプロジェクトでのことでした。
当時、私は設計責任者として数多くの人数が関わるチームを率いていました。
ある配管ルートの設計を変更したのですが、その情報共有が不十分だったのです。
解析的には問題がなく、私は「大丈夫だろう」と判断していました。
しかし――
製造現場は「この溶接は作業空間が狭すぎて品質が確保できない」
工務部は「変更された配管部品が予定納期に間に合わない。輸送スケジュールが崩れる」
品質検査部からは「この配管部品では検査ができない」
と現場から悲鳴があがったのです。
結果、製造ラインが一時停止し、数週間の遅延と大きな追加コストが発生しました。
あのとき、現場の職人が腕を組んで途方に暮れる姿を見て、胃が締めつけられるような感覚を今でも覚えています。
原因は、私自身が「設計上の合理性」にこだわりすぎ、現場の作業性や物流面での現実に配慮しなかったことでした。
つまり、部門間の利害調整がうまくいかず、情報共有が不十分だったのです。
若手エンジニアへのメッセージ
この失敗を経て、私は次の3つを大切にするようになりました。
1. 「ワンチーム」で動け
部署ごとに役割は違っても、ゴールは同じです。
情報を閉じ込めず、互いに共有し合うことが成功の鍵です。
プロジェクトマネジメントにおいては、コミュニケーションを徹底し、情報共有がスムーズに進んでいるか監視することが問題の早期発見につながります。
2. 現場に足を運べ
机上で正しい設計でも、現場では実現困難なことがあります。
現物を見て、作業者と話すことで真の課題が見えてきます。
プラントエンジニアリングのプロジェクトでは、クロスファンクショナルチームとのコミュニケーションを強化するために、目標設定や役割の明確化が重要です。
3. 失敗を糧にせよ
失敗は避けられません。
私も若手時代に構造部材の強度設計で計算ミスし、トラブルを起こした経験がありますが、その失敗から学び、次に活かすことで成長できました。
大切なのは、失敗を隠さずに共有し、次に活かす文化をつくることこそ、エンジニアとしての成長に繋がります。
おわりに
機械設計は、一人で完結する仕事ではありません。
解析、調達、製造、品質、工務、営業…
多くの仲間と協力し、時にぶつかり合いながら、一つの巨大な「モノ」を完成させる。
まさに総合格闘技です。
その過程は決して楽ではありません。
しかし、仲間と共に壁を乗り越え、製品が社会で動き出す瞬間の達成感は、何物にも代えがたい喜びです。
これからエンジニアを目指す皆さんも、ぜひこの「チームで挑むモノづくりの面白さ」を体験してみてください。
きっと、自分自身の成長と大きなやりがいを感じられるはずです。
それでは、また次回の記事でお会いしましょう!
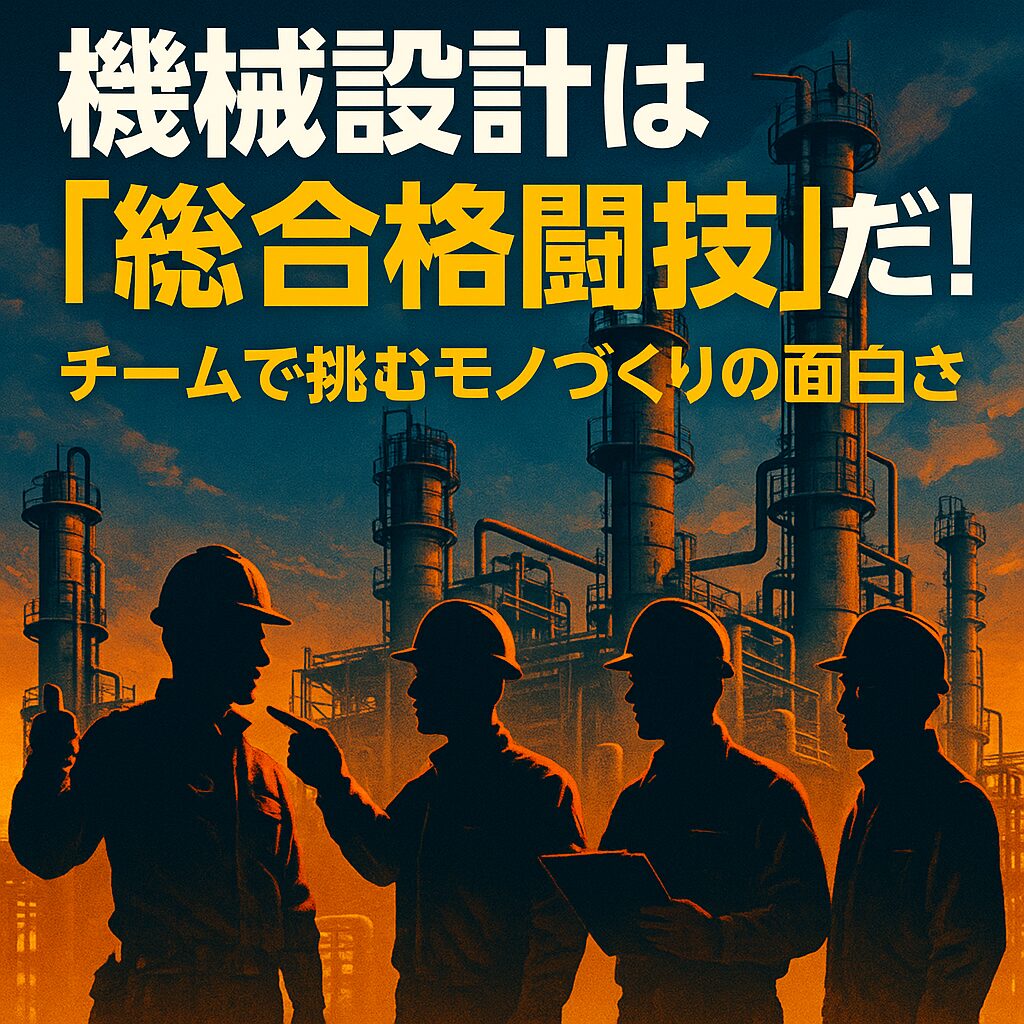
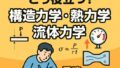

コメント