設計のゴールは“動くもの”ではなく“壊れないもの”
前回は「試作と評価」で、“失敗を数値化する技術”についてお話ししました。
今回は、設計の最終テーマともいえる「壊れないを設計する」という話です。
設計者にとって、動くものを作ることはもちろん重要ですが、真のゴールは“壊れないもの”を作ることです。
設計品質とは?――図面の線一本に込められた信頼
設計品質とは、図面の段階で品質を作り込むことです。
製造してから検査で“良品”を選ぶのではなく、最初から“良く作れる設計”にすることが求められます。
たとえば、穴とシャフトの公差を0.02mmに設定する理由が「振動を抑えるため」であれば、そこに設計品質が宿ります。
設計品質は、図面の寸法、材料、溶接方法など、すべてに「なぜそうするか」の意図が込められていることが本質です。
信頼性とは?――「長く安心して使える設計」を数値で考える
信頼性とは、製品が所定の期間、正常に動作する確率を示します。
たとえば、圧力鍋が「10年間、毎日1回使っても安全に圧力を保てるか」を考えることが信頼性設計の一環です。
信頼性を高めるためには、壊れにくい構造を考えるだけでなく、壊れる原因を予測しておくことが重要です。
圧力鍋で考える“壊れない設計”
圧力鍋を例に考えてみましょう。
もしパッキンが劣化して気密が保てなくなったら?
安全弁が詰まったら?
これらの“もしも”を事前に想定し、対策を講じることが信頼性設計の出発点です。
たとえば、安全弁を二重にする、パッキンを高温対応のシリコン製にするなど、壊れることを前提に考えた設計が求められます。
FMEA(故障モード影響解析)という考え方
FMEAとは「Failure Mode and Effects Analysis」の略で、故障の起こり方と影響を事前に分析する手法です。
具体的には、次の3つを整理します。
1. どんな壊れ方をするか(故障モード)
2. どんな影響が出るか(影響度)
3. どのくらい起きやすいか(発生頻度)
たとえば、圧力鍋の場合、故障モードとして「パッキンの破れ」を挙げ、その影響度や発生頻度を評価することで、重点的に対策すべきポイントが明確になります。
安全率と疲労設計――余裕をどう設計するか
設計でよく出てくる「安全率」は、壊れるギリギリの強さに対してどれだけ余裕を持たせるかを示す指標です。
たとえば、材料の引張強さが100MPaの場合、安全率2で設計すると50MPaまでしか使わないようにします。
安全率を高くすれば安心ですが、部品が大きく重くなるため、トレードオフの判断が必要です。
また、「疲労設計」は繰り返し荷重に耐えられるように設計する考え方です。
自転車のペダルを毎回こぐたびにフレームに小さな応力がかかりますが、これを考慮して設計することが重要です。
まとめ:設計品質とは、未来への約束である
「壊れない設計」は、数字だけで作るものではありません。
それは、使う人との“約束”です。
圧力鍋なら、家庭で安全に食卓を支えること。
自転車なら、毎日の通勤や旅を安心して楽しめること。
その約束を守るために、設計者は今日も図面の線1本に魂を込めます。
設計品質とは、“未来の安全を今つくる”こと。
信頼性とは、“その未来を信じてもらう力”です。
次回は、「設計レビュー事例 ― 現場で起こったリアルな学び」をテーマに、実際にあったトラブルと、そこから得た教訓をお話しします。
今回もブログを読んでいただきありがとうございました。
SNSでのシェア、大歓迎です。
経験から培った知識と知恵をここに記していきます。
引き続きよろしくお願いいたします。
さむらいすけ
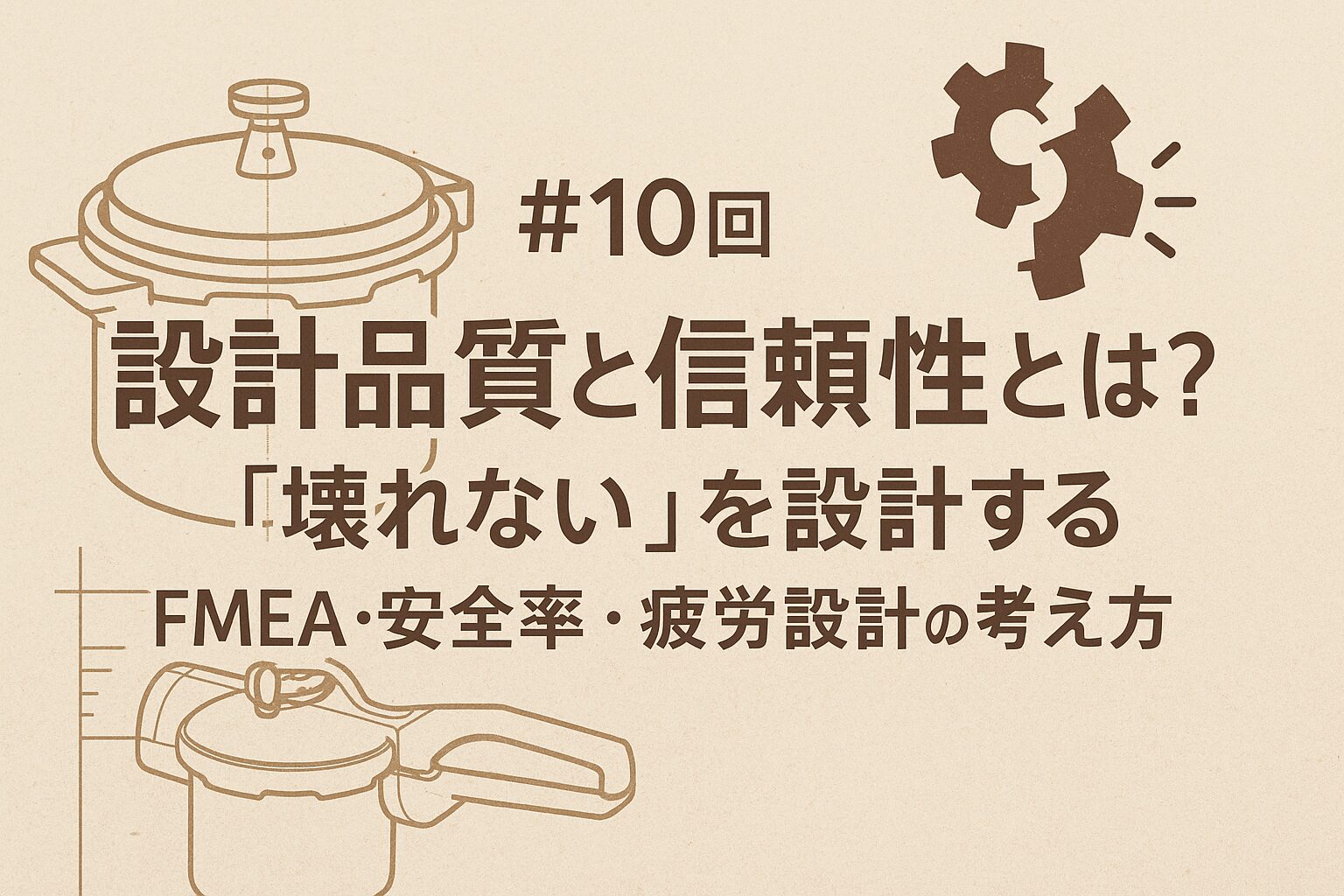
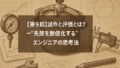

コメント