図面ができても、設計は終わらない
前回は「検査と組立」で、図面が現場で形になるときのリアルについてお話ししました。
今回のテーマはその次のステップ――試作と評価です。
設計者にとってこの段階は、まさに“真剣勝負”です。
机の上で練り上げたアイデアが、実際に動くかどうかを確かめる。
それが、試作と評価の仕事です。
試作とは――“仮説を現実で検証する”ステップ
試作とは、アイデアを実際に形にして、性能や使い勝手を確かめるプロセスです。
言い換えれば、“図面の実験”。
たとえば圧力鍋なら、
「この厚みで本当に700kPaに耐えられるのか?」
「圧力弁はどのタイミングで開くのか?」
といった仮説を確かめます。
試作は、失敗して当然。
むしろ、失敗しなければ得られない学びがある。
大事なのは、“なぜ失敗したのか”を明確にする姿勢です。
評価とは――失敗を恐れず、データで語る姿勢
評価とは、試作の結果を数値やデータで整理して判断する作業です。
感覚ではなく、数値で語る。
私が若手のころ、上司によく言われた言葉があります。
「失敗したなら、その“理由”をデータで説明しなさい。」
圧力容器の試験で、完成したときの重量が計算重量を超過したことがありました。
原因を探ると、材料ロットの違いで平均板厚が2%厚かった。
この“2%”という数字がわかれば、再設計も正確に行える。
評価の本質は、「感情の整理」ではなく「数値の理解」。
失敗を感情ではなく、データで受け止めるのがプロの設計者です。
圧力容器で考える「試作の目的」
圧力鍋の試作をするとき、最初から完璧なものを作ろうとするとコストが膨らみます。
そこで、まずは「小型モデルでの検証」を行います。
安全弁の動作、密閉性、温度分布を確認し、問題がなければ実機サイズに展開する。
ここでの目的は“成功”ではなく、“傾向をつかむこと”。
試作とは、本番前のリハーサルなんです。
小さな失敗を積み重ねて、大きな成功につなげる。
試験片・シミュレーション・プロトタイプの3つの手法
試作と評価には、大きく3つの方法があります。
1. 試験片(テストピース)による評価
小さなサンプルを作り、材料の強度・硬さ・疲労寿命などを確認します。圧力容器では、板材や溶接部の引張試験、衝撃試験などが代表例。「壊して学ぶ」ことが最も確実な評価です。
2. シミュレーション(CAE)
コンピュータ上で力や熱の影響を解析する方法。
たとえば、タンクの応力分布やたわみを事前に予測できます。
ただし、結果を過信してはいけません。
現物のデータでシミュレーションを“補正”するのが本当の使い方です。
3. プロトタイプ(試作機)
実際に動くモデルを作り、機能・操作性・安全性を総合的に評価します。
これら3つを組み合わせることで、設計の信頼性が飛躍的に高まります。
失敗を“数値化”するという考え方
「失敗しました」では設計は終われません。
大切なのは、“どの程度”失敗したのかを数値で把握することです。
たとえば圧力試験で断熱性能が想定より10%低かった場合、その“10%”が設計余裕(マージン)内なら許容できる。
逆に、5%でも安全率を割り込むなら、構造を見直す必要があります。
つまり、設計とは“定量的な反省”の積み重ね。
数字で語る習慣を持つと、再発防止もロジカルになります。
まとめ:試作とは「設計の失敗を最小コストで経験する」こと
試作と評価の目的は、成功を確認することではありません。
むしろ、“失敗を安く経験する”ためのステップです。
設計は必ずどこかで失敗します。
でも、その失敗を早く・小さく・数値で把握できれば、致命傷にはなりません。
私はいつも後輩たちにこう伝えています。
「失敗は“損失”ではなく、“投資”なんだ。」
試作で得たデータは、次の設計に必ず活きます。
だから、試作で悩むことは悪いことじゃない。
むしろ、悩んだ分だけ設計者としての“精度”が上がるのです!
(怒り心頭で叱責してしまうことも多々ありますが、理想はこうです。。。笑 反省)
次回は、「設計品質と信頼性 ― 壊れないを設計する」をテーマに、“長く使えるモノを設計する力”についてお話しします。
今回もブログを読んでいただきありがとうございました。
SNSでのシェア、大歓迎です。
経験から培った知識と知恵をここに記していきます。
引き続きよろしくお願いいたします。
さむらいすけ
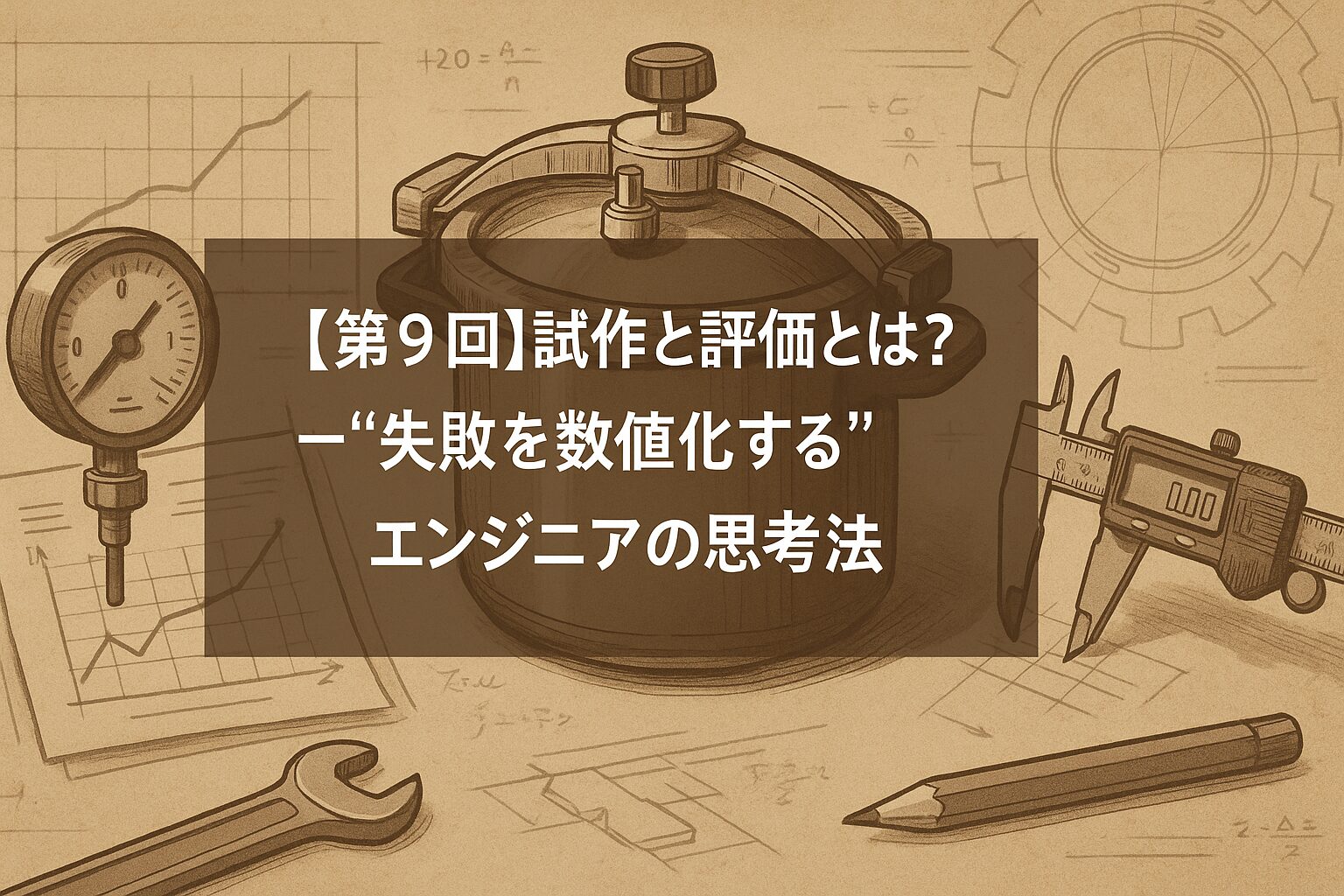

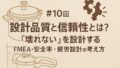
コメント