前回は「基本設計」で、機能・強度・コストのバランスを取る“トレードオフ思考”を紹介しました。
今回はいよいよ設計の最終段階
――詳細設計です。
構想設計で方向を決め、基本設計で性能を詰め、詳細設計で“形”を確定する。
つまり、図面とは設計者の最終メッセージなんです。
図面は「意思のある言葉」だ
若いころ、上司にこんなことを言われました。
「図面は、現場へのラブレターやで」
最初はピンときませんでしたが、今ならよくわかります。
図面とは、「自分が頭の中で描いた理想」を他人に伝える唯一の手段。
それが正確でなければ、いくら頭の中が完璧でも、現場には伝わりません。
つまり、詳細設計とは“図面という言語で考える”段階。
設計者の考え方や哲学が、線や数字として形になるんです。
詳細設計とは――形を“作れる図面”にする工程
「作れる」とは、加工できて、組み立てられて、検査できること。
単に形状を描くだけではなく、現場の作業性やコストも考える必要があります。
たとえば、圧力鍋の取っ手を設計するとします。
見た目だけを優先して複雑な曲面にすると、加工に時間がかかり、コストが上がります。
逆に単純すぎると、握り心地や安全性が損なわれる。
詳細設計の目的は、「図面の上で現実を再現すること」。
理想を形にするための妥協点を見極める力が問われる段階です。
寸法と公差――1mmの中に設計者の哲学がある
設計でよく聞かれるのが「公差(こうさ)」という言葉。
これは、部品の寸法がどの程度ズレてもOKかを決める範囲のことです。
たとえば、自転車のペダルの軸が穴にピッタリすぎると、回転しません。
逆に緩すぎるとガタついてしまう。この“すき間のバランス”をどう設定するか
――それが設計者の腕の見せどころです。
私が若手のころ、上司にこう言われました。
「100分の1mmを削るために、現場は1日働くんやで」
以来、私は「その公差は本当に必要か?」と自分に問いかけてきました。
設計者にとって公差は精密さの象徴ではなく、責任の証なのです。
加工性を考える――現場が喜ぶ図面を描け
どんなに立派な図面でも、作る人が困る図面はダメな設計です。
「加工性を考える」とは、製造工程を想像すること。
たとえば穴を開ける場合、工具を入れられなければ加工できません。
溶接構造なら、熱変形を想定して寸法を決める必要があります。
圧力鍋でいえば、内側の滑らかな仕上げは掃除のしやすさに直結します。
一方で、コーティングにこだわれば、コストが上がる。
この“現場感覚”を持つことが、真の設計者の成長ポイントです。
私は若手にこう言っています。
「現場を一度でも見て、加工者の声を聞いたら、図面の線が変わる」
現場を知らない設計は、ただの机上の理論です。
加工者の気持ちを想像できる設計者こそ、一流です。
部品構成の工夫――“分ける勇気”と“まとめる判断”
基本設計で決めた構造を、どう部品として分けるか。
これも詳細設計の大きなテーマです。
たとえば、圧力鍋のフタを一体で作ると部品数は減りますが、破損時の交換が難しくなります。
逆に細かく分けすぎると、組立や管理が煩雑になります。
このとき大切なのは、「保守性とコストのバランス」。
分ければ直せる、まとめれば安くなる。
どちらを選ぶかは、“使う人の未来”を考える判断です。
若手設計者へのメッセージ
図面はチームで作るもの図面は、設計者一人の作品ではありません。
製造、検査、営業、そしてユーザー
――多くの人がその図面に関わります。
だから私は、レビューでこう伝えます。
「自分の図面を、誰がどう使うかを想像して描こう」
自分の名前が書かれた図面を現場で見たとき、
“この線の意味を理解してくれている”と感じた瞬間の喜びは格別です。
それが、設計者としてのやりがいでもあります。
まとめ:図面はモノと人をつなぐ
設計者の手紙詳細設計は、単なる作業ではありません。
それは、技術と想いを人に伝えるための「手紙」です。
寸法や公差、線の一本一本には、設計者の考えと誠意が込められています。
そして、図面の向こうにはいつも“人”がいる。
作る人、使う人、守る人。その誰かを思い浮かべながら線を引く
――それが、設計者の本当の仕事です。
次回は、「デザインレビュー ― 失敗を未然に防ぐ仕組み」について。
どんなに良い図面も、レビューなしには完成しません。
“議論の中で育つ設計”を、一緒に見ていきましょう。
今回もブログを読んでいただきありがとうございました。
SNSでのシェア、大歓迎です。
経験から培った知識と知恵をここに記していきます。
引き続きよろしくお願いいたします。
さむらいすけ
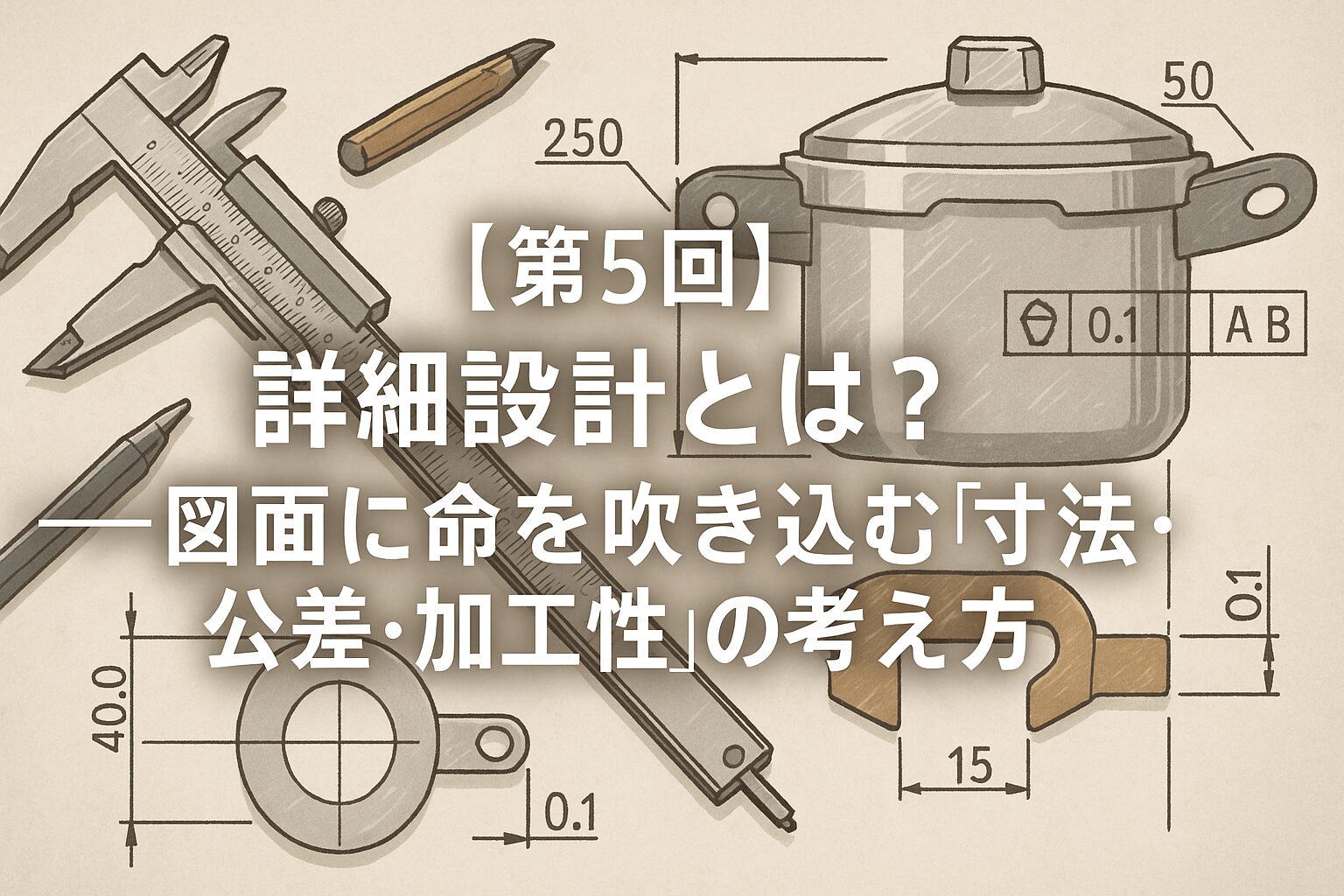


コメント