図面を描いた後に始まる、もう一つの仕事
前回は「デザインレビュー」で、チームで品質を守る文化についてお話ししました。
今回は、設計の最終段階――部品表と手配の話です。
図面を描いた後、実際に製品を作るための重要なステップが待っています。
部品表(BOM)とは――設計の意図を伝える“設計書の設計書”
部品表(BOM:Bill of Materials)は、製品を構成するすべての部品リストです。
設計者はここで、
「どの部品が、どの図面に対応し、どんな材料で、いくつ必要か」
を明確にします。
例えば、圧力鍋なら、フタ、本体、パッキン、安全弁、取っ手などが含まれます。
この一覧が曖昧だと、現場は混乱します。
「取っ手のボルトは何本必要?」
「材質はSUS?鉄?」
――こうした疑問がすべてBOMで解決できるようにしておくことが、良い設計の証です。
部品表は、設計の意図を現場に正確に伝えるための重要なツールです。
製番(せいばん)とは――製造を動かす“管理番号”の力
製番とは、製品1台ごとに付与される固有の番号です。
この番号を使って、図面・部品・納品書などを紐づけて管理します。
製番管理は、設計と製造をつなぐ共通言語であり、トレーサビリティを確保するうえで欠かせません。
設計者が製番を理解しておくと、品質トラブルが起きたときに強いです。
「どの製番のロットに問題があったか」をすぐに特定できるからです。
現場を守る設計者は、数字にも強い設計者なのです。
納期管理の現実:なぜ設計者がスケジュールを意識すべきか
設計者は“モノを作る人”でありながら、“時間を作る人”でもあります。
図面を1日遅らせれば、その後の加工・組立・出荷すべてが遅れるからです。
製造現場のスケジュール表を見たことがありますか?
一つの部品が遅れると、ドミノ倒しのように影響が広がります。
私が若手だった頃、図面の修正に時間をかけすぎ、製造ラインが止まったことがありました。4
そのとき現場のリーダーに言われた言葉が今でも心に残っています。
「設計の1時間は、現場の1日を止める。」
この言葉を聞いてから、私は“カレンダーを意識する設計者”になりました。
圧力鍋で考える「モノづくりの流れ」
圧力鍋も、設計から製造までの流れは同じです。
1. 設計(図面・仕様を決める)
2. 部品表作成(何が必要か洗い出す)
3. 手配(必要な部品を発注する)
4. 加工・組立(製造現場で実際に形にする)
5. 検査・出荷(品質を確認して送り出す)
この一連の流れがスムーズに回るかどうかは、設計者の準備力次第です。
BOMや製番を整えることは、製造の道筋を整備するようなものです。
道が整っていれば、トラブルがあっても迷わず進めます。
設計と製造の“橋渡し役”になるために
良い設計者は、図面が描ける人ではなく、人を動かせる設計者です。
部品表の整備、手配の確認、納期の共有
――それらを地味な仕事だと思わず、「次の工程の人への思いやり」と捉えてください。
私は現場の人たちにこう伝えられたことがあります。
「さむらいすけさんの図面は、組み立てやすい。」
その一言が、何よりもうれしかった!!
設計の本当のゴールは、“現場が動くこと”なんです。
まとめ:設計のゴールは“図面”ではなく、“使われる製品”
部品表や製番、手配、納期
――どれも地味な言葉に聞こえるかもしれません。
しかし、それらがなければ、設計はただの“机上の夢”で終わります。
設計者の仕事とは、「図面を描くこと」ではなく、“人と工程をつなぐ仕組みを設計すること”です。
図面の先には、現場があり、製品があり、そしてお客様がいます。
そのすべてをつなぐ線を描ける設計者になってほしい。
次回は、「検査と組立 ― 図面が形になる瞬間」。いよいよ、設計の答え合わせに入ります。
今回もブログを読んでいただきありがとうございました。
SNSでのシェア、大歓迎です。
経験から培った知識と知恵をここに記していきます。
引き続きよろしくお願いいたします。
さむらいすけ
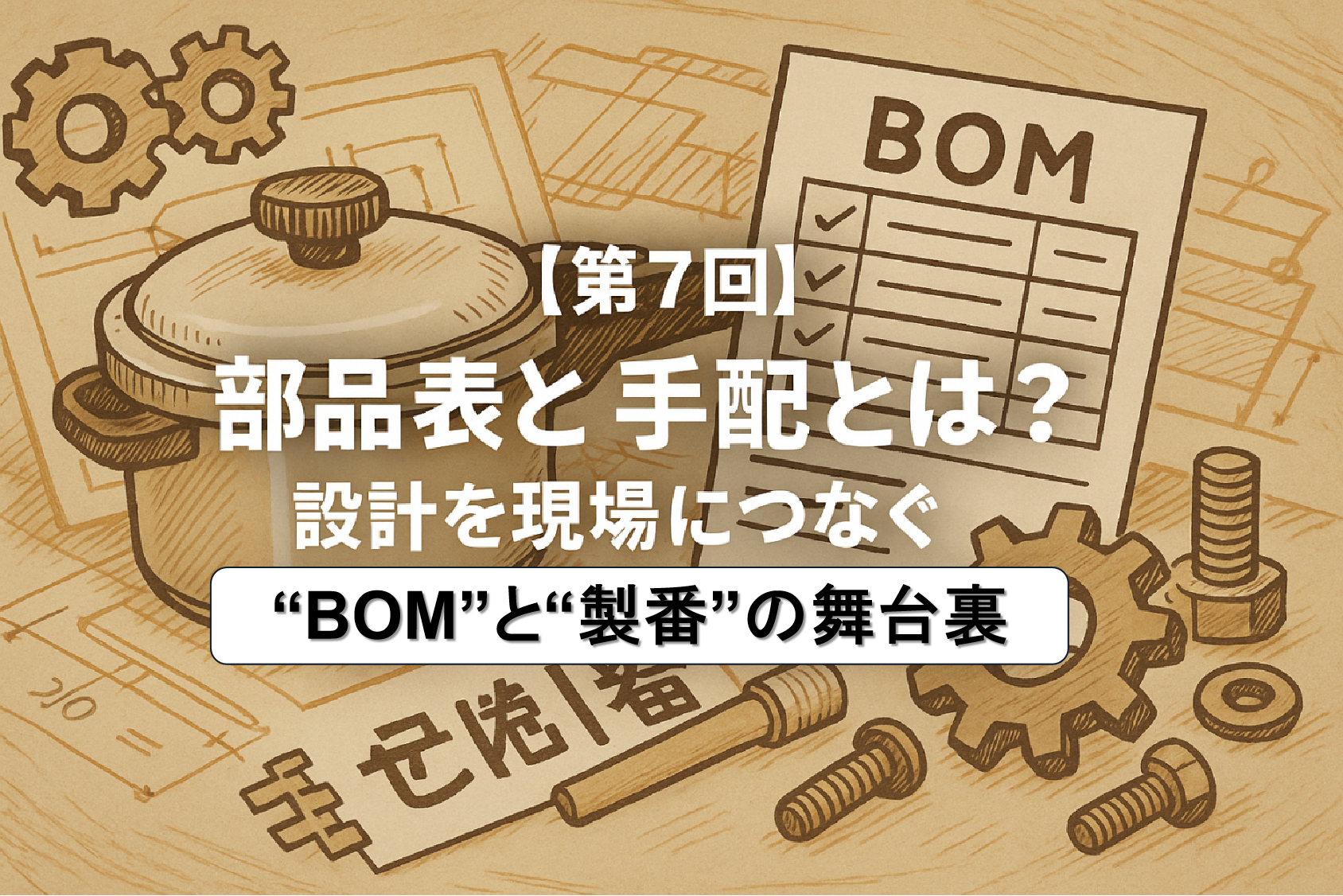


コメント