前回は「詳細設計」で、図面に魂を吹き込むことの大切さをお話ししました。
今回のテーマはその次のステップ――デザインレビュー(設計審査)です。
図面が完成した瞬間、設計が終わったと思ってはいけません。
実際の設計業務では、図面ができてからが本番です。
デザインレビューとは何か――“第三の目”で見る設計の安全網
デザインレビューとは、設計者以外の人が第三者の視点で図面をチェックする会議です。
製造現場、品質保証、安全担当など、さまざまな立場の人が集まり、図面の意図やリスクを話し合います。
このプロセスは、一人の知恵をチームの知恵に変える場なのです。
レビューを一言でいえば、「設計のダブルチェック」。
しかし、その本質はそれ以上に深いものです。
設計者は自分の図面に慣れ、何百回も見た線は間違っていても気づきにくいものです。
そんなとき、他の人の目が入ることで、思わぬ盲点が見つかります。
なぜレビューが大切か:一人の完璧より、チームの知恵
私はこれまで数々のレビューを経験してきました。
印象に残っているのは、若手の小さな疑問が大きな失敗を防いだケースです。
ある装置の配管系で、若手が「このバルブ、操作するスペースありますか?」と質問しました。
図面上では完璧でも、現場で組むとレンチが入らない位置でした。
このように、設計は「気づきの積み重ね」で成り立っています。
完璧な設計者などいません。
大事なのは、チームで完璧を目指す姿勢です。
圧力鍋で考える、見落としの怖さ
圧力鍋の安全弁が一箇所しかない設計を想像してみてください。
もしその弁が詰まれば、鍋は爆発します。
実際の製品では、必ず“二重の安全装置”が取り入れられています。
このような「冗長性」を考えるには、一人の頭では限界があります。
だからこそ、レビューという“他人の目”が不可欠なのです。
良いレビューとは?――「ダメ出し」ではなく「品質を守る対話」
レビューを“上司のチェック会”だと思っていませんか?
それは大きな誤解です。
本来のレビューは、「ダメ出し」ではなく「品質を守るためのチーム対話」です。
指摘を受けたら落ち込むのではなく、感謝することが大切です。
レビューで大事なのは、次の3つです。
1. 目的を共有する(「責める場ではなく、守る場」)
2. 意見を受け入れる(「自分の設計を疑う勇気」)
3. 感情ではなく事実で語る(「なぜ危ないのか」をデータで話す)
この3つを守るだけで、会議の雰囲気がガラッと変わります。
KY(危険予知)の発想を設計に活かす
製造現場では「KY(危険予知)トレーニング」という活動があります。
作業の前に「どんな危険が潜んでいるか」をみんなで話し合う仕組みです。
この考え方は設計にも応用できます。
レビューの中で
「この部品が折れたらどうなる?」
「電源が落ちたら安全側に倒れるか?」
と“もしも”を考えることが、設計版KYです。
想像力こそ最大の安全装置です。
まとめ:レビュー文化が組織を強くする
私は長年、国内外のプロジェクトでレビューを重ねてきました。
その経験から断言できます。
強い組織ほど、レビューが活発です。
レビューが形だけになってしまうと、
「やったことに満足して、何も変わらない」
という状態になります。
逆に、誰もが自由に発言できるレビューは、ミスを未然に防ぐだけでなく、チーム全体の学びの場になります。
設計者の成長とは、指摘を受けることを恐れず、仲間の視点を借りる力を磨くことです。
これこそが、未来の設計文化をつくる第一歩です。
次回は、「部品表と手配 ― 設計から製造への橋渡し」。
図面が現場に伝わる瞬間を、一緒にのぞいてみましょう。
今回もブログを読んでいただきありがとうございました。
SNSでのシェア、大歓迎です。
経験から培った知識と知恵をここに記していきます。
引き続きよろしくお願いいたします。
さむらいすけ
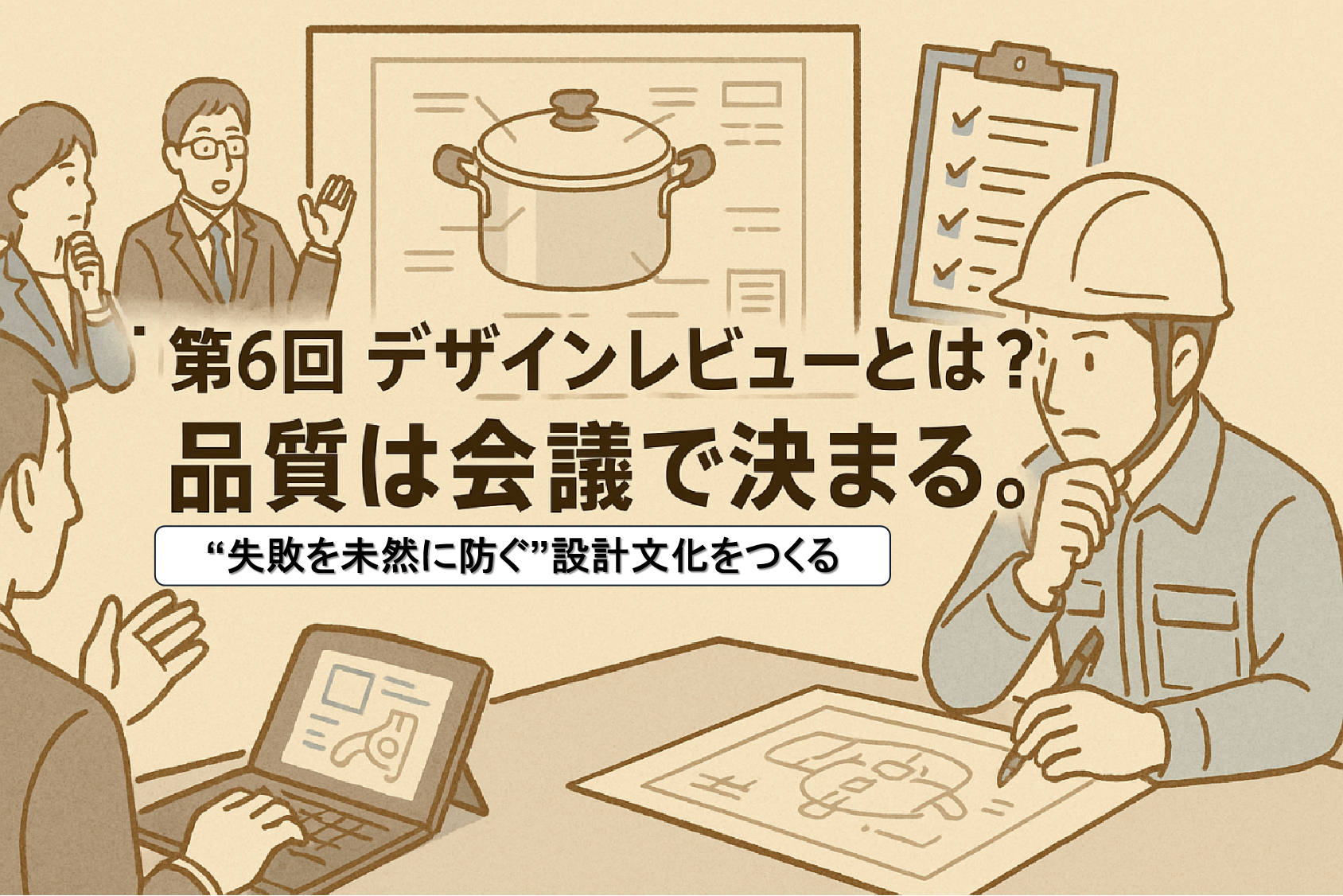
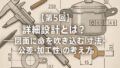
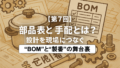
コメント