ここまでの連載で、機械設計の定義や役割、心構え、業務範囲、手順についてお話ししてきました。
今回のテーマは、私が長年の経験から特に大切だと思っている「シンプルでバランスのとれた設計」です。
若手時代の私は「機能を盛り込めば盛り込むほど、設計の価値が高まる」と思い込んでいました。
しかし実際はその逆で、複雑すぎる設計は壊れやすく、使いにくく、コストも膨らみます。
良い設計とは、シンプルでありながら必要十分な性能を発揮するものなのです。
シンプルな設計のメリット
1. 故障が少ない
部品点数が多いほど、壊れる可能性のある箇所も増えます。
例えば自転車の変速機。
多段ギアは便利ですが、複雑になればなるほどチェーンが外れるリスクが増えます。
用途が街乗り中心なら、必要以上の段数はむしろデメリットです。
2. 製造コストを下げられる
部品を減らし、加工を簡素化する。
それだけで製造コストは大きく下がります。
圧力容器の設計でも、余計な部品を削ったり、溶接箇所を減らしたりすることで、コスト削減と信頼性向上を同時に達成できる場合があります。
3. ユーザーにとって使いやすい
操作方法がシンプルであれば、ユーザーは迷わず安心して使えます。
圧力鍋の例でも、「安全弁の操作が複雑」より「自動で安全に蒸気を逃す」方がずっと安心です。
バランスをとるという考え方
シンプルさを追求する一方で、「必要な性能まで削ってしまう」のは本末転倒です。
設計者は常に「安全・性能・コスト・使いやすさ」のバランスを意識しなければなりません。
例えば航空機のエンジン設計。
軽くすることは燃費向上につながりますが、安全率を削りすぎれば命に関わる事故につながります。
逆に安全率を過剰に取れば重量が増えて性能や経済性を損ないます。
設計とは、トレードオフの中で最適解を探す作業なのです。
私の現場経験から若手時代に設計したあるプラント配管で、部品を複雑にしすぎた結果、現場で組み立てに手間がかかり、納期が大幅に遅れたことがありました。
その後、現場の職人さんに「もっとシンプルにしてくれれば助かるのに」と言われ、目が覚めました。
その経験以来、私は設計を進めるときに必ず「この部品は本当に必要か?」「もっと簡素にできないか?」と問い直すようにしています。
まとめ:シンプルさとバランスの重要性
良い機械設計に欠かせないのは、「シンプルでバランスのとれた設計」です。
シンプルにすることで故障が減り、コストも下がり、ユーザーにとって使いやすくなる。
ただし必要な性能を犠牲にしてはいけない。
常に安全・性能・コスト・使いやすさのバランスを意識する。
これが、現場で長く使われる信頼性の高い設計につながります。
若手への一言メッセージ:シンプルさの中に工夫を
「設計=複雑で高度なもの」と思いがちですが、本当に優れた設計は驚くほどシンプルです。
シンプルさの中に工夫と知恵を込めること、それが設計者の腕の見せどころです。
次回は最終回として「これまでのまとめと若手へのメッセージ」をお届けします。
お楽しみに!
さむらいすけ
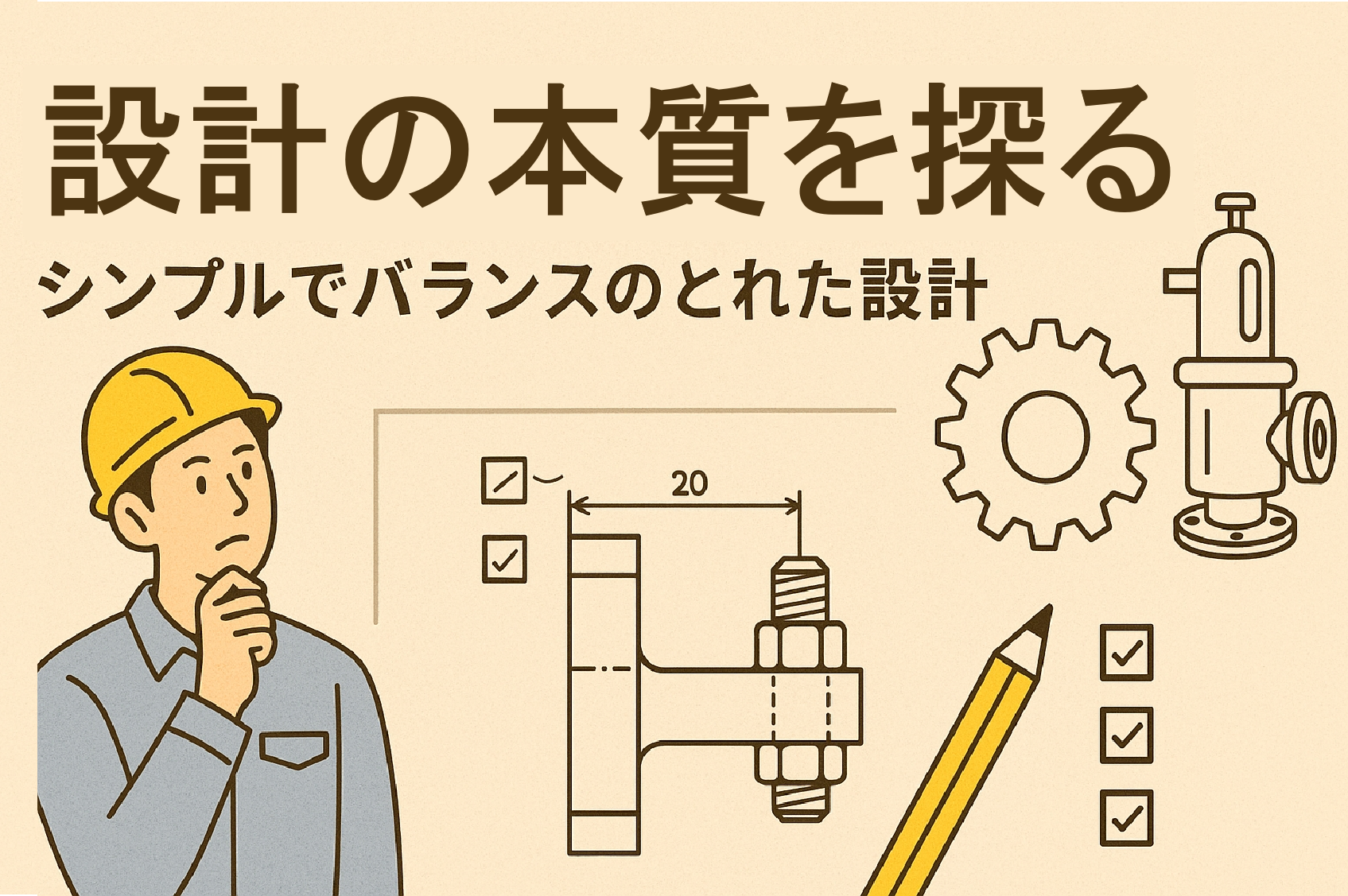


コメント