私が長年、圧力容器の設計に携わってきた経験から、若いエンジニアや学生の皆さんに「設計って、なんだか難しそう」「図面を描く仕事でしょ?」という誤解を解きたいと思います。
実際の設計は、図面を描く前の“考える時間”がすべてです。
この連載を通じて、機械設計の本質をお伝えします。
機械設計とは何をする仕事か
機械設計とは、一言で言えば「機械の機能を実現するために、形・材料・仕組みを考える仕事」です。
たとえば、「コーヒーメーカーを作りたい」と言われたとき、設計者は「お湯をどう加熱するか」「水の圧力をどう制御するか」「掃除しやすい形にするには?」といったことを考えます。
設計者は、使う人の立場に立って、目的を“形”に翻訳する人なのです。
図面はその翻訳結果に過ぎません。
図面の裏にある「考える」仕事
多くの人は、設計=CADで線を引く作業だと思いがちです。
しかし、線を引く前に考えることが山ほどあります。
具体的には、どんな材料を使えば壊れにくいか、加工する人が作りやすい形か、10年使っても安全でいられるか、コストと性能のバランスは取れているか。
このように、設計とは「トレードオフ(両立しない条件)の中で最適解を探す作業」なのです。
計算力や知識だけでなく、人との対話力や想像力が求められます。
圧力鍋で考える「設計の本質」
身近な例を挙げてみましょう。
圧力鍋は、鍋の中の圧力を上げて調理時間を短くする仕組みです。
しかし、圧力を高くしすぎると危険なので、「どのくらいの厚みのフタが安全か」「どんな材質を使えば耐えられるか」を考える必要があります。
この“安全と使いやすさのバランス”を決めるのが設計です。
自転車も同様です。
軽く作ればスピードは出ますが、フレームが弱ければ折れてしまいます。
逆に頑丈に作れば重くて漕ぎにくい。
設計者はこの「軽さ」と「強さ」のちょうどいい点=最適設計を探しているのです。
若手エンジニアへ伝えたいこと
私が若手のころは、図面の寸法を一つ決めるだけでも緊張しました。
「これで本当に大丈夫だろうか…?」と不安で眠れなかった夜もあります。
しかし、経験を積むうちに気づいたのは、「正解は一つではない」ということです。
設計には必ず“理由”があり、その理由を自分の言葉で説明できるかどうかが大事です。
設計は「上司に言われた通りに描く作業」ではなく、自分の頭で考え、納得のいく形を提案する創造的な仕事です。
失敗を恐れず、自分の考えを出すことが一番の成長につながります。
まとめ:機械設計は“人の想いを形にする仕事”
これまで、たくさんの機械を設計してきましたが、どれ一つとして「ただの金属の塊」ではありません。
その裏には、使う人、作る人、守る人――たくさんの想いがあります。
機械設計とは、そうした人々の想いを形にし、社会を動かす“仕組み”を作る仕事です。
この連載では、企画から設計、製造、検査、評価まで、実際のプロセスを順にたどりながら、「設計の現場で何が起きているのか」「なぜその考え方が必要なのか」を、できるだけわかりやすくお話ししていきます。
次回は、「企画の段階――お客様の“本当の要求”をどう見抜くか」について掘り下げていきましょう。
さむらいすけ


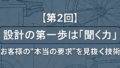
コメント