図面を描く前にすべきこと
前回は「機械設計とは何か」というテーマで、設計は“考える仕事”だとお話ししました。今回は、その「考える」前の大事なステップ――“企画”の段階についてお話しします。
図面を描く前にすべきこと
私が若手だったころ、上司からこう言われたことがあります。
「いい設計をしたいなら、図面を描く前に“何を作るのか”を100回考えろ」
当時は意味がわかりませんでした。
しかし今になって思うのは、設計の8割は「聞くこと」と「考えること」なんです。
どれだけ立派なCADを使っても、相手の要求を正しく理解していなければ、それはただの“自己満足の図面”です。
「第一仕様」と「要求」はちがう
たとえば、お客様が「静かに動くポンプがほしい」と言ったとします。
これをそのまま「静音ポンプ」として設計に入るのは早計です。
静かに動く、とはどの程度の静かさ?
どんな場所で使うのか?
コストは?
寿命は?
安全性は?
ここで出てくるのが、「要求」と「仕様」の違いです。
要求(ニーズ):お客様が「こうしてほしい」と思う願い
仕様(スペック):それを実現するために設計者が定める条件力つまり、設計者は「静かに動く」という“言葉の裏”にある本当の意図を探らないといけません。
お客様が言葉にしない“本当のニーズ”を探る
機械設計の現場では、お客様がすべてを明確に説明できるとは限りません。
むしろ、「困っているけど、原因がよくわからない」ということのほうが多いのです。
―そんなとき、設計者は探偵のような視点を持つ必要があります。
ヒアリングをするときは、以下の3つを意識すると良いです。
1. 使う現場を見る(実際の環境や作業者の動きを観察する)
2. 使う人に質問する(操作の不満点を直接聞く)
3. 客過去のトラブルを調べる(改善のヒントを探す)
これらを通して見えてくる「現場の真実」こそが、本当の要求です。
圧力鍋の設計に学ぶ――使う人の立場に立つ視点
圧力鍋を例に考えてみましょう。
ユーザーの要求は「時短でおいしく煮込みたい」。
それに対して設計者は、圧力を高めて沸点を上げるという仕組みを考えます。
でも、実際に使ってみると「フタが開けにくい」「怖くて扱いづらい」という声が出てくる。
このとき、「圧力が高ければいい」だけではダメなんです。
安全に、誰でも、簡単に使える構造を設計することが、真の要求への回答になります。
つまり、良い設計とは“スペックを満たす設計”ではなく、“使う人が満足する設計”なのです。
若手エンジニアに伝えたい「3C思考」
企画段階で役立つ考え方に、「3C分析」というものがあります。
マーケティングの世界で使われる言葉ですが、設計者にもぴったりです。
Customer(顧客):誰が、どんな環境で使うのか?
Competitor(競合):他社の製品や過去の設計はどうか?
Company(自社):自社の強みをどう活かすか?
この3つを整理すると、「自分たちはどんな価値を提供できるか」が見えてきます。
私も若手のころ、上司に「設計とは“会社の戦略を図面で表すこと”だ」と言われたことがあります。
まさにその通りです。
技術まとめ:設計は「聞く力」と「想像力」で決まる
優れた設計者は、計算が早い人でも、CADが上手な人でもありません。
相手の話をよく聞き、「なぜそう言うのか?」を考えられる人です。
設計は、人と人との信頼で成り立っています。
相手の気持ちを想像し、その想いを形にする
――それが私が考える企画設計です。
次回は、「構想設計――実現できそうな“あたり”をつける」についてお話しします。
いよいよ設計の中核、アイデアを形にするステップに進みましょう。
さむらいすけ
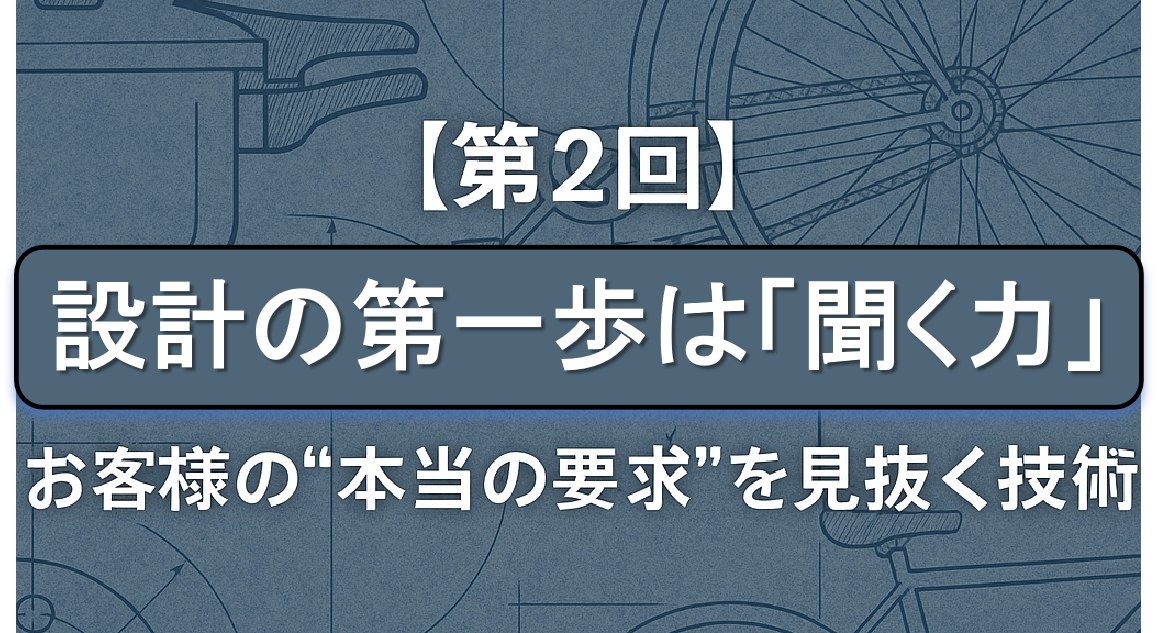


コメント